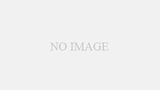『吉川家什書』
「昨日十五日、内府様、直に山中へ押し寄せられ、合戦に及び、即時討ち果たされ候。昨日、江州に至り、二手に分かれて乱入なされ候。(中略)青野原に至り、悉く先陣衆打出、最前陣所へは内府入り移るべく候。然るところ、筑中(小早川秀秋)御逆意はや色立ち仕合候。それについては、大垣衆も山中大谷少(大谷吉継)の如く、心もとなく之由に引き取り候。・・・・・・・」
彦坂元正・石川安通連署書状
「筑前中納言殿(小早川秀秋)・わき坂中書(脇坂安治)・小河土佐父子(小川佑忠・佑滋)、此四人御味方申し、うらきり(裏切り)を致し候、則敵敗軍仕り」とあり、小早川、脇坂、小川の裏切りによって関ヶ原での合戦は決着がついたことが当時の文書にはっきりと記されていることが分かる。
関ケ原合戦の大坂方の敗北は、小早川・脇坂らの裏切りであったことが、これらの文書にはっきりと記されている。
しかし、両者の裏切りがどうして敗北につながったのか?
裏切りは関ヶ原全体からみれば局所であり、それがなぜ全体の敗北につながったのか?
それは、彼らの守っていた場所が中山道の隘路、山中であり、一番防御しなければならない要の場所であったからである。
彼らは大谷吉継とともに関ヶ原での一番の急所を守っており、それが崩れたことで、中山道から徳川軍の侵入を許してしまい、大坂方の各陣の後ろからの侵入が可能になったからである。
ただ、関ヶ原合戦前日までは松尾山には大垣城主伊藤盛正とその兵が入っており、15日もそのまま伊藤が入っていれば、裏切りなどはなかったはずで、後のような展開にはならなかったであろう。
一にも二にも、松尾山に小早川が入ったことが、大坂方敗北のすべての原因となったことは間違いない。
この詳細については、拙著『竹中重門と百姓たちの関ヶ原』を参照していただければと思う。