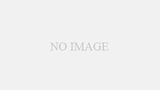南宮山の毛利軍が動くか動かないかの鍵は山麓の安国寺が握っていたことは間違いない。
毛利軍は関ヶ原合戦において二度動くチャンスがあった。
一つは、家康軍が関ヶ原合戦の前日の深夜、目の前の中山道を通った時、そしてもう一つは合戦当日関ヶ原に入った家康軍の背後を突く時である。
家康は、大将の毛利秀元が南宮山の山頂に隔離されている状況から、毛利軍は動く意思がないと確信したといわれているが、それでも合戦はふたを開けてみなければ分からない。
しかし、家康の読み通り毛利軍が動くことはなかった。
これは、関ヶ原に布陣している石田三成らに対する背信行為であり、実質的に家康軍を勝利させる大きな力となったことはいうまでもない。
それでは、なぜ毛利軍は動かなかったのか?
それは、安国寺の判断であったことは間違いない。
だが、安国寺は勝手に自分で判断を下せる立場にはなかったことは事実であろう。
安国寺にはどこかの時点で不戦の命が下されていたのだ。
それを下せる立場にいたのは、大坂の毛利輝元しか考えられない。
慶長の山城 関ヶ原松尾山城11
 ブログ
ブログ