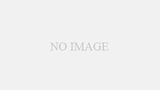しかし、ここにきて、その三成の構想を大きく妨げる出来事が発生した。
その一つが、竹中重門が徳川方に付いたことにより菩提山城を失ったこと、そして、三成が築いた関ヶ原での防衛線の情報が同じく竹中を通じて、徳川方に筒抜けになってしまったこと。
さらに、もう一つが大津城の京極高次が叛旗を翻し、城に立て籠もったことである。
毛利輝元の養子で、毛利、吉川、安国寺を率いて伊勢に出陣していた毛利秀元は美濃口の危急の知らせに、9月7日美濃垂井に入ったが、布陣した場所は南宮大社の背後にある険しい山とその山麓であった。
『細川忠興軍功記』に「伊勢口より、毛利殿人数・土佐長曽我部・長束大蔵・秀頼様御弓鉄砲衆、此人数都合三万にて南宮山へ押上陣取候」とある。
垂井は関ヶ原に入るための中山道の塧路であり、そこを押さえれば、徳川軍の関ヶ原への侵入を食い止めることができる。
その意味では、毛利の布陣は一応は理にかなったものといえる。
三成の構想を妨げた三つの出来事
 ブログ
ブログ