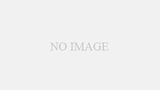甲斐では永正元年(一五〇四)に「飢饉」(『高白斎記』)、永正二年(一五〇五)「疫病」(『塩山向岳禅庵小年代記』)永正七年(一五一〇)「大地震」(『高白斎記』)という災害が絶え間なく起こっていたが、信玄の父信虎はそれでも、その後、国内の有力領主大井氏と今井氏と四年の間、抗争を続けた。
だが、この間にも永正十二年十月「大雪・大雨」による飢饉(『妙法寺記』)、永正十三年七月「震動」(同前)、永正十四年七月「暴風洪水」(『高白斎記』)、永正十五年「天下飢饉餓死」(同前)、永正十六年「日本国飢饉」(『妙法寺記』)と、災害やそれに伴う物価の高騰によって人々が命を維持できないほどの状態が続いていた。
そんな甲斐の政情の不安定さをみてとった隣国駿河の福島氏は、一万五千といわれる大軍を率いて大永元年(一五二一)九月、甲斐に乱入するが、信虎はそれを迎え撃って、大将の福島氏を討ち取り、残兵を駿河に追い返すことに成功した。
この戦いで自信を深めた信虎は、今度は国外、関東での上杉氏と北条氏との抗争に介入し、大永四年(一五二四)関東に兵をすすめ、北条氏と戦った。
しかし、この間も大永二年「作毛殊のほか悪し」(『妙法寺記』)、大永三年「都留郡大飢饉」(同)などの厳しい状況は変わらず続いていた。
この後、信虎は信濃に兵を進めるが、その間に嫡子晴信(信玄)が重臣たちと共謀して、クーデターを起こし、信虎を駿河に追放した。
『妙法寺記』には信虎の駿河追放について「(信虎が)余りに悪行を成らせ」たためであり、「地下・侍・出家・男女共喜び満足致し候こと限りなし」と民衆が一様にこのことを大きく歓迎したことが述べられている。
信虎は永正四年(一五〇七)十四歳で武田家の家督を継いでから天文十年(一五四一)信玄によって引退させられるまでの三十四年間、休むことなく戦いに明け暮れていた。
この間、甲斐は打ち続く戦乱と天変地異、さらに飢餓、疫病と民衆は疲弊し、厭戦気分はピークに達していた。
しかも、信虎はそんな民衆の怨嗟の声にほとんど耳を傾けることなく、内戦を勝利すると今度は他国に兵を繰り出していく有様であった。
信虎は飢饉の最中見返りのない戦争を長期間繰り広げることにより、甲斐を疲弊させ、民衆の支持を失っていき、それが、信玄による追放劇につながっていったのである。
気候変動と戦国時代③ 武田信玄 父信虎を追放す
 ブログ
ブログ