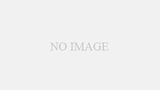慶長五年八月廿八日、福島正則、池田輝政から家康に書状が寄せられた。
去る二十三日、岐阜城を攻め落としたので、出馬を要請するというものだった。
岐阜城は石田方の重要拠点で織田秀信(信長の嫡孫)が守り、周囲の竹ヶ鼻城や犬山城はそれを守る城として織田の与力大名らが守っていた。
特に犬山城と竹ヶ鼻城はそれぞれ木曽川対岸にあって敵の渡河を阻む役目を任されていたが、犬山城に入っていた加藤貞泰、竹中重門らが家康側に寝返ったため、福島正則、池田輝政らは何らの妨害を受けることなく木曽川を渡り、対岸の竹ヶ鼻城を攻め落とし、一気に岐阜城下の総構えを破り、岐阜城に迫り、たった一日の攻防で岐阜城を落とすことに成功した。
石田方は岐阜城に援軍を送ったが、福島、黒田らの勢いに押され敗北。重要拠点の岐阜城を失ってしまうことになった。
結果、石田方は大垣城に兵を集め、福島らと対峙することになった。
一方、岐阜城を力で落とした福島らは、家康に出馬を迫ると共に、兵を進め、大垣城と対峙する美濃赤坂岡山を本陣としその周辺に陣を布いた。
彼らの次のターゲットは石田三成の居城でもあり石田方の最重要拠点でもある佐和山城攻めであり、それには関ヶ原の隘路を突破しなければならなかった。
美濃赤坂は、中山道を扼する要地で、大垣城の石田軍が中山道を移動して関ヶ原へ進軍することを阻止する位置にあった。
福島らは家康を赤坂の陣所で待つことにしたが、ここでも家康は彼らの暴走が気がかりであった。
家康は勝利にはやる彼らを押さえ、家康が到着するまで何らの動きもせぬよう井伊直政らに書状をもって言い含めた。
家康は岐阜城が落ちた以上、自らの出馬なしには前線が収まらないことを確信し、ついに九月一日江戸を出発することを決めた。
しかし、関東・東北では上杉・佐竹と伊達・最上の情勢が予断を許さない状況となっていた。
この点は家康にとって大きな不安材料ではあったが、これ以上出馬が遅れれば、血気にはやる福島らは家康なしで大垣城の三成らと戦うことになるであろう。
上方部隊は豊臣大名中心であり、家康のいない戦いはただの私戦、豊臣内部同士の戦いになる。
ここでは勝利を得たとしても、家康が勝ったことにはならないのであった。
家康はここで意を決し、上方への出馬に踏み切った。
同時に最前線宇都宮城を守っていた秀忠にも出馬を要請し、宇都宮には留守部隊として結城秀康を残すこととした。
秀忠は上杉攻めの為に終結していた徳川三万五千の本軍を率いて行くことになった。
関ヶ原合戦「慶長記」を読む20 岐阜城落城
 ブログ
ブログ